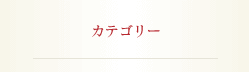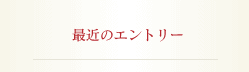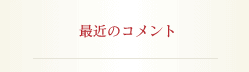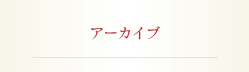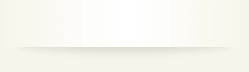| 格式と文様 |
2014年4月12日
|
昨日に引き続き着物の「きものの文様」のお話です。
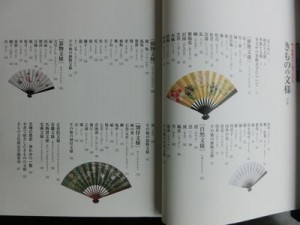
着物の格式にあわせて帯を選びます。
きものは、織りのきものよりも染めのきものの方が格が上
帯はその反対でして「染めのきものに織りの帯」が
格を合わせた装いになります。
ワタクシの帯を参考にしながらでもってすすめてゆきます。

引き箔「霞に方形散らし」は訪問着や付け下げに。
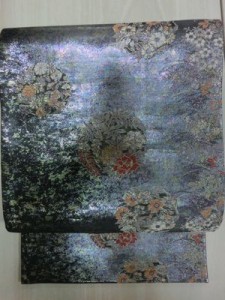
焼箔の「花文」も訪問着や付け下げに。

マットな輝きの箔の幾何学模様。
これは、小紋にもありな感じです。
植物文様は、季節が限られています。

秋海棠の帯はグラデーションが美しいことです。


「櫻花占い」はリバーシブルです。
「矢羽根」を表にして桜柄は少しみせることにしています。
桜を待つ頃から咲き始めるまでの、春先にだけ出来る帯です。

「霞取り」川の流れの中に夏椿。夏の帯です。
着物の柄には風景文様も多くあります。

プラチナ箔の「楼閣山水」。
この帯の中に遠近感ある画が描かれています。
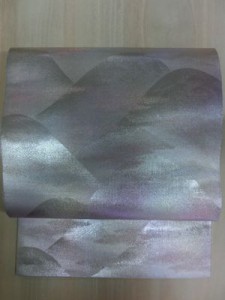
「遠山風景」大和絵風の丸みのある
なだらかな稜線が描かれています。


「幽玄世界」はリバーシブルの帯です。
割付文様は、同じ模様の規則的な繰り返しが美しいことです。。

青海波文・菱文・亀甲とおめでたい柄の「裂取り」。

「金箔散らし」の帯は裏が三角の繰り返しの鱗文になっています。
鱗文は魔よけ厄除けの意味があるそうです。
「この着物にこの帯がいいね」と話しながら
場面を想定しながら伊達衿と帯あわせもしてみました。
こんな風に、時間できると「和ごころ勉強」しています。
この日、鶴ママ手作りのお弁当もいただきました。

中央は桃の花、お庭で咲いたそうで
「これは食べたらだめよ」と^^。
なすのごまびたし絶品でした。
栄養満点のお弁当ありがとうございました。
投稿者 rin5chan : 2014年4月12日 カテゴリー: めしませ着物 | コメントはまだありません »
« きものの文様|メイン|桜の兼六園からひがし茶屋街へ »